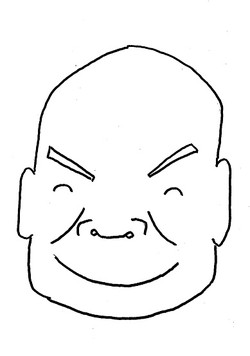「リア王」観劇
このまえ、なんで演劇というものを観始めたかみたいな話をしましたよね。たしかに東京というところには、実に大小のいろんな劇場がありまして、常に魅力的な芝居の演目がかかっているんですけど、生のお芝居というのは、なかなかそんなにたくさん観れるもんではないんですね。そもそも基本的に高額だし、せっかくチケットを取っても、急に行けなくることもあるし、映画みたいには、そう何度もかけられないわけです。
そんな中で、どうしても観たいものは頑張って観るみたいなこともあるんですけど、あとは、こういう広告映像みたいな仕事をしていると、知ってるスタッフとかキャストとかが、舞台にかかわっていたりして、観せていただくこともわりとあります。
いつも思うのは、本物のライブのパフォーマンスには特別な緊張感があって、二度と同じものは観れないという高揚感もあるんですね。
先月、東京芸術劇場のプレイハウスで上演されていた「リア王」を観てきたんですけど、これは、なかなかに重厚で興味深い演劇体験でした。シェイクスピアの古典をイギリスの演劇監督のショーン・ホームズという方が演出をなさっていまして、科白はかなり難解ではあるのだけど、日本の俳優陣は達者で、十分にその期待に応えております。
現代社会を思わせる美術に衣装、そこに斬新な舞台装置も相まって、一つの世界が作り出され、観客は大きな舞台の中に、じわりじわりと引き込まれる感覚です。気がつくと、厄介に思われた難解な科白にも、やがて慣れております。
言ってみれば、これぞこの舞台でしか味わえぬシェイクスピア体験というもので、たぶん、のちのち語り草になる「リア王」ではないかとも思ったわけです。まだ全国公演中ではあるのですが。
何故この芝居を観に行ったかというと、このリア王を演じる段田安則という役者の舞台は、欠かさず観に行ってるからでして、今回もそうですが、つくづく上手い役者だと思います。
この人とは不思議なご縁があって、わりと長いことお付き合いしておりますが、知り合ったのは、おそらくお互い20代の頃で、私の方がちょいと2学年ほど上なのですが、その頃、段田さんが入ったばかりの劇団・夢の遊眠社は、世の中で評判になり始めていて、私がかかわっていたCMに、ちょっと遊眠社の役者さんたちに出演していただいたのが最初でした。それから劇団の方達とは年齢も近くて仲良くしていただき、時々出演をお願いしたり、ナレーターをやってもらったりしておりましたが、そんなきっかけで私「夢の遊眠社」の公演はたぶんほぼ全部観ておりました。
戯曲の中における段田さんの配役はいつも重要な役で、野田秀樹さんの書く台本というのは、だいたいものすごい量の台詞なんだけど、ある時は美しく、ある時はコミカルに、ある時は刺さるように、そしてその詩のような言葉群は、彼らの肉声で的確に観客に届けられておりました。
「夢の遊眠社」は、1992年に惜しまれながら解散したんですけど、その後も段田さんは舞台を中心に役者の仕事を続け、今に至ります。もちろんテレビでも映画でも、強く印象に残る仕事をしておられますし、声も良いのでナレーションの仕事のオファーも多いのですが、やはりこの人は舞台の仕事が好きみたいです。私は彼のたいていの芝居を観ておる一人のファンですが、その芝居は深いなあと思います。これは同業の役者さんからして、よくそうおっしゃってます。
彼の芝居が始まって科白を云い始めると、その周りの空気をそこに集めてしまうような時がありますね。ただ、舞台を降りると普段は全くそういうオーラのない人でして、家も近所なんでたまに会うこともあるんですけど、ほんとにただの一般の人にしか見えないです。
そんなことで、今まで数々の名芝居がありますが、ライブの舞台というのは、その時間のその風景として記憶に留めておくしかありませんね。今回の「リア王」もいろいろ余韻があって、さぞ記憶に刻まれることでしょうが、実は2年前にどうしても観れなかった舞台があってですね。それは今回のショーン・ホームズさん演出、段田安則主演の「セールスマンの死」だったんですが、その時私コロナに感染してついに観にいけなかったんですね。思っていた通り非常に評判になりましたから、ほんとに悔しかったんですけど、こればっかりはどうやっても観れませんから、そうゆうもんなんですね、芝居って。