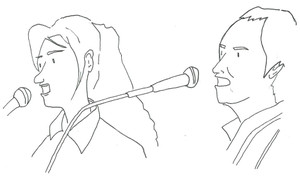「PERFECT DAYS」という映画
まあ、昔から映画が好きで、常になんやかやといろんな映画を観てるんですが、コロナもあってこのところ本数は減っております。ただ根が好きなもんでわりと観てはいるんですけど、見渡してると、映画界には国内も国外も新しい才能が次々出てくるし、技術の進歩も目覚ましく、映画館へ行けば常に新しい何かを見せてくれます。
ただ、古今東西の多くの映画を観てきて、その表現のさまざまな手の内も知っていたり、そもそもこっちも歳をとってきて、感受性が鈍くなってきていることもあり、最近、その作品そのものが、深くこちらの内側に入ってくることがあんまりなくてですね。ただ読後感として、面白かったとか、いい映画だったとかいうことはあるんだけど、なんだか若い時の、観た後に忘れられない映画みたいな経験は、このところなかったんですね。
それで、この春に観た映画の話なんですけど、「PERFECT DAYS」という映画でありまして、なんだか久しぶりに響いたんですね。
東京で公共トイレの清掃員をしている、ある物静かな男の日常を、カメラはただ見ているのですが、映画はその仕事ぶり、暮らしぶりをドキュメントのように淡々と描きます。ただ、観客としての自分は、なぜかそこから目を離すことができません。気がつくと自分は、主人公の平山という男のすぐ隣にずっといて、ゆっくりその世界に引き込まれて行きます。
男は下町の安アパートに一人で暮らし、暗いうちに起きて、清掃の仕事の装備をした自分の車で都心へと向かいます。トイレ掃除が終わると、下町に戻り、銭湯に入って、立ち飲みで一杯、アパートに帰って静かに本を読む暮らしです。一人の部屋には、大量の本とカセットテープが整然と並んでいるのです。
そこからはラストに向かって少しずつ、まわりの人とのかかわりの中、映画としての様相を呈していきます。そして、この映画全体に、木漏れ日の映像が大切な役割を果たしており、音的には、車の中にカセットテープで流れる60年代〜70年代のロックが重要な脇役になっています。ある意味、音楽映画とも言えるくらいに。
この映画は12月に公開される予定で、東京国際映画祭のオープニングを飾ることになっていて、すでに世界中から高い評価を受けています。
どうして、こんなに魅力的な映画が出来上がったのか。それはいろいろあるんですが、やはり、監督・脚本のヴィム・ヴェンダース氏によるところ大ではあります。
1984年「パリ、テキサス」
1987年「ベルリン・天使の詩」
1999年「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」
2011年「Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち」等
現代映画における最も重要な一人とされるドイツの名匠。
これらの作品は映画ファンであれば誰もが観ていると思います。
ヴェンダース氏は、この物語の中に住む平山という清掃員を紡ぎ出しました。この映画にとって最も重要な存在。そのキャストは彼がずっとリスペクトしてやまない俳優、役所広司です。
映画を観て、このキャスティングなしに、この作品はあり得ないと思えます。カンヌ国際映画祭で、最優秀主演男優賞を受賞したのも、納得できます。まったく、この国が世界に誇れる俳優といえます。
それと、ヴィム・ヴェンダースという映像作家が、長い歴史の中で、ずっと日本を、東京を注視し続けていることは、この映画が生まれる背景として非常に重要なことであります。よく知られていることですが、彼は映画監督の小津安二郎を大変敬愛していて、1985年に小津映画の中にある失われたユートピアを求めて東京を彷徨い、「東京画」というドキュメント映画の名作を作っていますが、これも今回の映画につながる何かを感じずにはおれません。
映画を観終わった時に、すごく揺さぶられたのだけど、今までに観た映画には全く感じなかった、何か別な新しいものに出会った気がしたのは確かで、この作家にはいつもそういうところがあるのですが。今回、共同脚本とプロデュースを担当したクリエーターの高崎さんが云われてたんですけど、シナリオ作りの途中で、この映画のテーマは何かとヴェンダースさんに聞いたとき、監督は、それが言えるなら映画をつくる必要はないよと、微笑んだそうです。
なんだかモノをつくる時の姿勢というのでしょうか、深い仕事ですよね。
この度ちょっと自慢したかったことが、この素晴らしい映画の製作プロダクションを私共の _spoon.inc が担当したことでして、いえ、私は全く何もしていないのですが、うちの会社の頼りになる後継者たちが、プロデューサーとして、若いスタッフとして、みっちりお手伝いさせていただいたんですね。映画界の世界的な巨匠、スタッフ、キャストたちと、この仕事を達成させることは、これから大変な勲章となると思います。
しかしながら、実際の制作・撮影の現場は、無茶苦茶えらいことだったと聞きました。監督は、ドイツが誇るインテリでアーティストで優れた教養の持ち主なのに、常に謙虚で誰からも尊敬される本物の紳士なのですが、撮影が始まると、ただの我儘なじいさんだと、皆が親しみを込めて言っています。そうじゃなきゃあんな映画は撮れないとも思いますが。
これは映画とは関係のない話ですが、ヴェンダースさんのチャーミングなエピソードをひとつ。
そもそも、ヴィム・ヴェンダースさんとは、カメラマンでもある彼と彼の奥様が日本で写真展をおやりになった時に、その写真展のセッティングを弊社でやらせていただいたことがあったんですが、2006年に表参道ヒルズの開業にあわせてのイベントでしたから随分前ではあります。それから何年かして、夏にご夫妻が来日されたことがあって、ちょうど神宮の花火大会の頃で、うちの会社からよく見えるもんで、是非どうぞとご招待したんです。この時200人くらいはお客さんが来ていたと思いますが、私、屋台じゃないですけど、鉄板で広島風お好み焼きを焼いておりまして、多分70枚くらいは焼いたと思うんですけど、そしたら、そこに長蛇の列ができちゃって人が溢れてたんですよ。そうすると、列の一番後ろに、背の高い長髪の紳士が、ちゃんと紙皿と割り箸持って並んでるんですね、世界のヴィム・ヴェンダースが。で、まわりの奴らもまさかそんな大変な人がいるとは思ってないから、まあ、ほったらかしにされてるんですね。本人もなんだかニコニコして機嫌良さそうなんですけど。で、私あわてまして、
「ヴェンダースさーん、あなたはスペシャルゲストだから、一番前に、ここにきてくださーい。」
て、よくわからない英語で叫んだんですね。
そしたら、ニコニコしながら、まわりの人にスイマセン、スイマセンと言いながらやって来まして、私が焼いたお好み焼きをオイシイ、オイシイと言って食べてくださいまして、、
昔から憧れて大ファンだった映画監督に、私の焼いたお好み焼きを食べてもらったという、ただの自慢話ですけど。