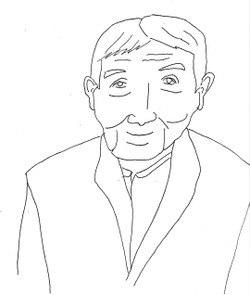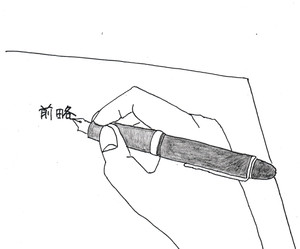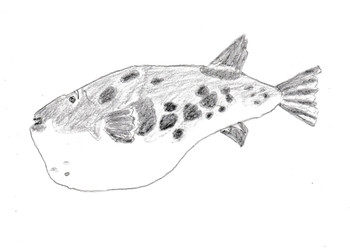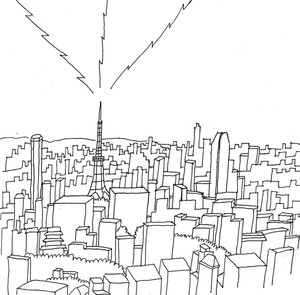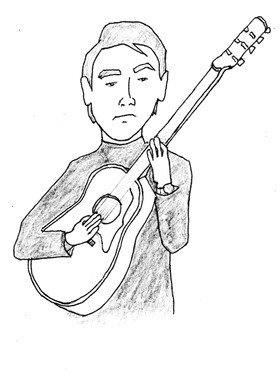70年も前の映画なんだが
 「七人の侍」新4Kリマスター版 3週間限定上映というのがありましてですね。そりゃこうしちゃあいられねえってわけで、朝の9時から新宿の東宝まで行ってきました。
「七人の侍」新4Kリマスター版 3週間限定上映というのがありましてですね。そりゃこうしちゃあいられねえってわけで、朝の9時から新宿の東宝まで行ってきました。
皆さんよくご存知の黒澤明監督の大作で、世界中が絶賛した名作なんですけど、私が生まれた年の公開ですから、もう70年も前の映画なんです。
そういうことなんで、もう何遍も観ていて、シーンによってはセリフも覚えてるくらいなんですが、そういえば、大きなスクリーンで3時間半、通しで観たのは遥か昔のことで、もう一回ちゃんと観ておきたいとは思っていたんですね。
最初に観たのはよく覚えてないんですけど、たぶん中学か高校の頃、映画館でリバイバルの上映だったか、もしかしたらテレビだったか忘れてますが、とにかくものすごく心を揺さぶられて、茫然自失になったことを覚えています。
なんだかよくわからないけど、観ているうちにあの世界に入っていって、侍と農民たちと一緒に、野武士軍団と闘っている自分がいるんですよね。そういう感覚になる映画ってそうはなくてですね、ずいぶん久しぶりに見ても、やっぱりそういうふうになるから不思議です。
監督もスタッフも俳優さん達も、もうあらかたいらっしゃらないんですけどね。
時代劇ではあるんですけど、出てくる人たちや風景に、妙にリアリティがあって、前からなんでだろうとは思っていたのですけど、それはもちろん技術的にすごく上手に作られてるんだろうが、ひょっとして、それってこの映画が封切られた時代にも関係あるのかなとも、思ったんですよ。
この物語はシナリオ上、どうしても生きるか死ぬかの戦いを描いており、一般人を巻き込んだ小さな戦争の中で、次々に人が死んでいくことになります。主人公の七人の侍も、残ったのは3人だし、野武士は全滅だし、村人達もずいぶん亡くなります。
この映画の持っているリアル感は、制作側の意図とかというより、あの敗戦からまだ9年しか経っていない、あの時代の空気が映っているような気がしたんですね。私が生まれたばかりのあの頃、世相は色濃く戦争を記憶してたと思うんです。
ずいぶん長尺の映画なんで、多少忘れてる場面があったり、シーンの順番が思ってたのと逆だったりすることはあるものの、その世界感がしっかりと記憶と結びついている映画であることは間違いないですね。
先日亡くなったうちの父は、映画好きで、私がずいぶん小さな時から、自分が見たい映画には、かまわず連れて行く人でして、私も機嫌よく黙ってずっと観てる子だったようで、洋画も邦画もたくさん見せてもらったんですけど、子供心にクロサワカントクという人のことはおのずとインプットされたようでして、やがて少し大きくなって、この名作に出会ったと記憶しています。
すごく個人的なことなんですが、何年も前に自分たちで作った小さな会社の代表を務めることになった時に、あんまり覚悟ができてなくて、どんなリーダーを目指すのが良いのだろうかと思って、いろんな人のことを巡り浮かべた時に、この「七人の侍」で志村喬さんが演じた島田勘兵衛のことを思い出したんです。実際にそこから何かを参考にしたわけじゃ無いんですけど、気持ちのどこかに島田官兵衛という人を覚えているようにはしようと思ったんですね。
自分が生まれた年に封切られた映画なのに、何度観ても、同じ読後感だなあと思いながら映画館の出口の方へ歩いていたら、後ろからポンと肩を叩いた満面笑顔の人がいて、よく見たら何十年もお世話になっている、新宿の老舗居酒屋「池林房」の店主のトクちゃんでした。
やっぱ、この年代の人は、この映画を何遍でも観に来るんだなと思ったんですね。